2050年「脱炭素化」達成に向けて、住宅でも「ゼロエネルギー化」(=再生可能エネルギーを自分でつくり、年間のエネルギー収支をゼロにすること)がますます求められています。
では、無理せず、がまんせずゼロエネルギーハウス(ZEH)を実現するにはどうしたらいいか?
エネルギーの専門家が自宅をZEHとして新築した体験をとおして、具体的にアドバイスします。
省エネ・断熱の仕方から、太陽光発電・太陽熱利用、薪・ペレットの活用法、蓄熱・蓄電……ゼロエネルギー住宅をどうつくるかという実践的な知識とともに、どうすれば脱炭素化、ゼロエネルギー化が前進するか、というモノサシも得ることができます。
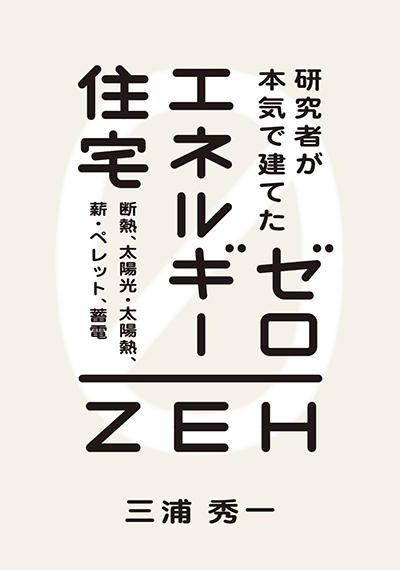
研究者が本気で建てた ゼロエネルギー住宅
断熱、太陽光・太陽熱、薪・ペレット、蓄電
三浦秀一 著
定価:2,420円(税込)
ISBNコード:9784540181627
発行:2021/1
出版:農山漁村文化協会(農文協)
判型/頁数:A5 240ページ

山形県山形市にある著者の家。在来木造軸組工法、延床面積139㎡、外皮平均熱寒流率UA値0.28[W/(㎡/K)]

著者の家の薪ストーブ

夏の日射しをさえぎるためのタープ

冬の日射しを取り入れるために、2階バルコニーの床板を取り外している

著者の家で使う2年分の薪の量(縦2m×横6m)。1年は乾燥が必要

山形エコハウス。山形県が環境省の補助を受け、東北芸術工科大学と連携し、2010年に建設したモデル住宅
著者
三浦 秀一(みうら しゅういち)
東北芸術工科大学建築・環境デザイン学科教授。1963年兵庫県生まれ。早稲田大学理工学部卒業。1992年同大学院博士課程修了。博士(工学)。東北芸術工科大学講師、准教授を経て、現職。住まいとまちの環境計画が専門。地球温暖化をはじめとする様々な環境問題から、人-すまい-まち-地球というつながりを見つめ直し、新しい住まいやまちの未来を提案している。
目次
- まえがき
- 01 私のエネルギー自給実践録
- 1 自給と快適さの追求は両立できる
- 2 断熱で冬の世界が変わる
- 3 エネルギー自給で自然の見方が変わる
- 4 ゼロエネルギー住宅の前提は省エネ
- コラム① 日本のエネルギー自給率と市民の危機管理
- 02 省エネ住宅を正しく理解する
- 1 古民家はエコ住宅? 夏を旨とすべし?
- 2 風が通れば涼しくなるか?
- 3 住宅のエネルギーは冷房より暖房が多い
- 4 日本の寒い家は命の危険をもたらす
- 5 省エネは我慢、快適はぜいたく?
- 6 あなたの快適な温度は?
- 7 高気密住宅は不健康?
- 8 暖房依存の家から「断熱」で暖まる家に
- コラム② エネルギーにお金をかけるか、家にお金をかけるか
- 03 省エネ住宅を建てるポイント
- 1 省エネ住宅の断熱性能
- 2 省エネ住宅の鍵を握る窓
- 3 健康・快適かつ省エネを実現する住宅の断熱水準
- 4 夏に夜の冷気を取り入れる窓
- 5 夏の庇はもっと長く
- 6 冬の庇はもっと短く
- 7 今ある家を断熱リフォーム
- コラム③ どこに頼めば省エネ住宅になるか
- 04 エネルギーのものさしでくらべる住宅
- 1 断熱機能にはものさしがある
- 2 エネルギー全体のものさし
- 3 熱というエネルギー
- 4 オール電化住宅はエコ住宅か?
- 5 一次エネルギーというものさし
- 6 二酸化炭素というものさし
- 7 お金というものさし
- 8 暖房の省エネ
- 9 給湯の省エネ
- 10 換気の省エネ
- コラム④ 森のエネルギーはCO2ゼロ
- 05 ゼロエネルギーにする太陽エネルギー
- 1 住宅の屋根は太陽光発電の適地
- 2 太陽光発電は損か得か?
- 3 太陽光発電と固定価格買取制度(FIT)
- 4 太陽光発電が電気の価格破壊をもたらす
- 5 太陽熱温水器でお風呂の自給
- 6 太陽熱温水器か太陽光発電か
- 7 どれだけ太陽光発電があればゼロエネルギー住宅になるか
- コラム⑤ 太陽以外の再生可能エネルギー
- 06 森のエネルギーの暖房
- 1 世界のバイオマスエネルギー
- 2 日本の薪炭利用の歴史
- 3 木をエネルギーにしてはげ山にならないか
- 4 木で発電
- 5 薪ストーブによる輻射の暖かさ
- 6 薪ストーブの進化
- 7 ペレットストーブ
- 8 日本のペレットと地産地消
- 9 薪の単位と品質
- 10 ペレットの品質
- 11 薪、ペレット、エアコンのランニングコスト(燃費)
- 12 薪・ペレットストーブの排ガス対策
- 13 薪ストーブにするか、ペレットストーブにするか
- コラム⑥ 環境に良い薪ストーブの使い方
- 07 省エネ住宅でこそ活きる森のエネルギー
- 1 森のエネルギーで暖房の自給
- 2 省エネ住宅では薪やペレットがどれぐらい必要か
- 3 省エネ住宅で薪づくりも楽に
- 4 薪、ペレットストーブを入れる前に断熱を
- 5 木のストーブと高断熱高気密住宅での換気
- 6 ストーブ1台で全館暖房
- コラム⑦ 伝統的木造工法と省エネ住宅
- 08 ゼロエネルギー住宅と蓄エネ
- 1 蓄電池でオフグリッド(独立電源)にできるか?
- 2 蓄電池は元が取れるか?
- 3 太陽光発電をお湯で蓄エネ
- 4 エコ住宅と電気自動車で電気のやりとち
- 5 FIT後の太陽光発電の環境負荷
- 6 木のエネルギー貯蔵力
- 7 省エネルギー基準と木の暖房
- コラム⑧ 3つの需要ギャップを埋めるエネルギー貯蔵
- 09 木のエネルギーで本当のゼロエネルギー住宅
- 1 政策としてのゼロエネルギーハウス(ZEH)
- 2 木質ストーブを入れてゼロエネルギーを実現する
- 3 本当のゼロエネルギーハウスとは?
- 4 災害にも強いエコ住宅と薪
- 5 ゼロエネルギー住宅を建てるといくらかかるのか?
- 6 暖房給湯のできるバイオマスボイラで本当のゼロエネルギー住宅に近づく
- 7 集合住宅こそゼロエネルギー住宅に
- 8 バイオマス地域熱供給でゼロエネルギータウン
- コラム⑨ 電力会社を切り替えてゼロエネルギー住宅に
- おわりに
書評・反響
■ 読者カードから ■
----- 2021/9 -----
時機を得た出版物だと思う。出版企画者はお手柄。技術記録概観できて良い。ただし個人が実践するには、より詳細なデータが必要。それにしてもレポートとしては良い!
(千葉県 会社員 70代 男性)
----- 2021/3 -----
里山作りを考えている。その中心となるEZHを建てようと思っているので、大いに参考になっている。ソーラー発電の中でソーラーシェアリングの事もふれてほしかった。
(京都府 半農半X 70代 男性)
----- 2021/9/21 -----
一級建築士/『みかんぐみ』共同代表/『エネルギーまちづくり』代表取締役|竹内昌義さんが選ぶ、SDGsと地球環境に触れる本5冊の選書 3〜5
『ソトコト』特集 | 有識者たちが選ぶ未来をつくる本|サスティナブル・ブックガイド
----- 2021/6 -----
『住む。』No.78(2021年夏号) Sumu Square "Books"
便利さをとるか、エコロジーをとるか。環境を考えるときこの板ばさみはつきものだが、こと、家とエネルギーの関係においては、さまざまな研究と技術ですでに両立が可能だ。では、がまんすることなく、ゼロエネルギーで暮らせる家を建てるには具体的にはどうすればいいのか。
省エネの仕方、断熱と気密の重要性、再生可能エネルギーを使ったエネルギー自給の方法。専門的な内容が、一般の建て主に向けてわかりやすく説かれる。簡明な章立てとわかりやすい図表による裏付け、そしてゼロエネルギー住宅での約10年間の暮らしのデータと体感が、あくまでも平たく記されていく。
太陽光発電を屋根に載せ、薪ストーブで暖をとって自宅で使うエネルギーを用立てることで、私たちは消費者から生産者へと立場が変わる。エネルギー源を吟味し、需給のバランスを図るという、これまで国や電力会社の役目だと思ってきたことが、家庭にも託されることとなるわけだ。この立場の変換を自覚することが、この本の隠れた要点なのではないかと思う。
目先の目的はもちろんゼロエネルギーの住まいづくりなのだけれど、その先に日本のエネルギー自立と再生可能エネルギーへのシフトが見通せる。そして、遠い他人ごとだったエネルギー政策が、実は自分たちの手の中にあることに気づく。エネルギーを自給するということはそういうことだ。この本が住宅のつくり手ではなく、住み手に向けて書かれた理由はきっとそこにある。
----- 2021/5 -----
『月刊NOSAI』 2021年6月号 自著自薦(三浦秀一)
最近、脱炭素やカーボンニュートラルといったことばが頻繁に飛び交うようになりました。地球温暖化の影響と思われる災害が世界中で頻発し、それを防ぐには二酸化炭素の排出を減らすどころか、ゼロにしなければいけないということが世界の共通目標となったからです。それにしてもゼロにするのは難しいだろうと思う人は多いのではないでしょうか。実は住宅からの二酸化炭素排出をゼロにするのは意外に簡単です。実際、私がそういう家で、快適に過ごしているから言えることなのです。この本は我が家を例にとりながら、ゼロエネルギー住宅のデータや費用までを詳しく書いています。
ポイントは何かというと、一に断熱、二に再生可能エネルギーです。断熱をしっかりすれば暖房のエネルギーを減らしてくれるのと合わせて、冬場の寒さから解放してくれます。どの程度断熱すればいいのかが問題ですが、その目安となる水準を本書で紹介しています。そして、再生可能エネルギーというと住宅では太陽光発電が一般的で、最近は蓄電池も入れるというような話がよく聞かれます。この本では薪ストーブとペレットストーブという木のエネルギーについて詳しく説明しています。そして、本当のゼロエネルギー住宅にしようとすると、この木のエネルギーがどうしても必要になります。なぜなら、冬になってエネルギー消費が増える時期に太陽光発電の発電量は落ちるからです。そんな冬最強の再生可能エネルギーが木のエネルギーなのです。ところが、日本ではそうした木のエネルギーの効果がきちんと評価されていません。また、新しい高断熱住宅での薪ストーブとペレットストーブの使い方も従来とは違ってきます。この本は、木という地域の資源を使った新しい時代のゼロエネルギー住宅のつくり方をお伝えするものです。

