スギ人工林を広葉樹と混交林化することで
生態系サービス(水質浄化、持続的な生産力、
洪水や渇水防止、クマを留めおく、など)
は大幅に向上する。
そのメカニズムを実証的に解明し、
混交林化の具体的方法も提言する。
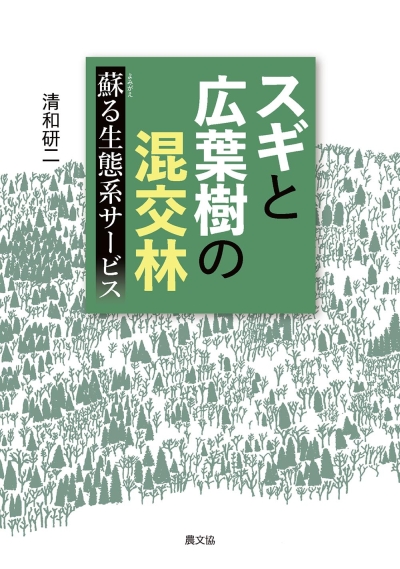
蘇る生態系サービス
清和研二 著
定価:2,750円(税込)
ISBNコード:9784540211584
発行:2022/9
出版:農山漁村文化協会(農文協)
判型/頁数:A5 208(カラー96)ページ
全国一律のスギ人工林造成は、天然林が元々もっていた生態系サービス(水質浄化、持続的な生産力、洪水や渇水防止、クマを留めおく、など)を大きく後退させている。
東北大学のスギ人工林試験地での詳細な比較研究により、混交林化によって本来の森林の機能が回復することを実証的に解明。あわせて天然更新と人工植栽による持続可能な混交林づくりの具体的方法を示す。

自生山スギ天然林(宮城県大崎市鬼首)

自生山スギ天然林 スギは濃い緑色に見える。所々で小さな集団をつくるが、おおむね単朴的(点状)に広葉樹と混交している。

自生山スギ天然林のスギ大径木 ブナやミズナラなどと混じり、直径1mを超える通直なスギが聳え立っている。

自生山スギ天然林ではスギやブナなどが高い林冠から下層まで連続的に見られ、他にも多くの樹種が階層構造をつくっている。
清和 研二(せいわ けんじ)
東北大学名誉教授。山形県鶴岡市黒川生まれ。
北海道大学農学部卒業。北海道林業試験場、東北大学大学院農学研究科教授等を経て現職。
単著に『多種共存の森』『樹は語る』『樹と暮らす』『樹に聴く』(以上、築地書館)、
編著・共著に『発芽生物学』『森の芽生えの生態学』(いずれも文一総合出版)などがある。
■ 読者カードから ■
----- 2023/1 -----
清和氏の本はすでに3冊読んでいますので迷わず購入しました。実家は弟に継いでもらい、私は山林田畑をすべて弟にゆずりましたので、14年前の定年退職後に伐跡山林を6.7ha購入し、森林組合のスギ、ヒノキを植えてもらった間にケヤキ、山桜、トチノキ、カツラ等を植えています。それで、本書の内容は良く理解できます。広葉樹苗はその土地のでは当然ですが、広葉樹苗生産地はかぎられていて、やむをえず長野、岩手等から購入しました。広葉樹苗の生産体制整備がのぞまれます。またケヤキの立性苗は日本のせまい歩道にあわせた品種がムサシノ○号と出回っていますが、材質は不明で、宮崎県で発見された立性ケヤキの接木苗を植えました。立性苗の改良も望まれます。しかし、私も歳でそろそろリタイアです。今後の手入れを迷っています。
(福岡県 70代 男性)
■ 書評・ネットでの紹介など ■
----- 2023/3/14 -----
中島岳志「トーキングキャッチャー」第102回 ~スギ人工林を考える~
で本書が紹介されました(音声配信中)
全国各地の人気ラジオ番組が参加♪ 聴く!読む!参加する!
豪華トーク満載の「AuDee(オーディー)」
***** リンクはありません *****
●『日本農業新聞』2022年10月9日 書店へいらっしゃい(三省堂書店農林水産省売店)
「森林再生を考える本」として紹介